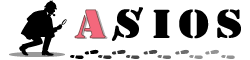『謎解き超常現象Ⅳ』の「デリーの鉄柱」に関する補足や追加解説
調査・執筆:若島利和
本稿は『謎解き 超常現象Ⅳ』で取り上げた「デリーの鉄柱」に関する項目31、32についての補足と解説である。
もともと、この2本の記事は「デリーの鉄柱」に魅入られた筆者(若島)が、趣味学習用に書き連ねていた「家庭内超常レポート」のようなテキストから、要点を絞り2本の【伝説】と【真相】形式に編集したものである。
必然的に未掲載部分がかなり存在しており、お蔵入りさせておくには惜しいと思うところもあり、それらを再編集したものを公開する。
なお、おさらいも兼ねて項目31と項目32を、下記目次の(1)と(2)で簡単に整理した。この(1)と(2)は、本編のように【伝説】と【真相】の形式ではなく、伝説と真相をまとめて大枠を紹介したものなので、各論の中身や論拠、保護性錆の組成図や参考資料等は書籍本編を参照して欲しい。
また下記目次の(3)~(6)は新しく【伝説】と【真相】形式にした未掲載部分等である。(6)は「デリーの鉄柱」が造られたグプタ朝の技術水準をざっと紹介する意味もあって書いた、おまけ記事と思っていただきたい。
(3)追加【伝説と真相1】 99.72%の高純度鉄に関する謎と誤解
(5)追加【伝説と真相2】 巨大な鉄柱の製造方法に関する謎と地中部分の深さ
(6)追加【伝説と真相3】『マハーバーラタ』と「デリーの鉄柱」本当は凄いグプタ朝
書籍【項目31】「デリーの鉄柱」は超文明の産物:要約
デリーの鉄柱とは5世紀初頭に北インド東部でヴィシュヌ神への捧げものとして造られた6トン7メートルの巨大な鉄柱である。700年ほどそこにあったが、侵入したイスラム勢力に抜きとられ、現在のデリー郊外に移設され現在にいたる。

現代では「錆びない鉄柱」として有名だが、西欧世界では19世紀まで世界最大の鉄建造物としても名を馳せてきた。1970年代にデニケンらが古代の宇宙飛行士説と絡めて紹介したこともあり、もはや解決済の「地味で退屈なオーパーツもどき」と認識している者もいるだろうが、それは誤解である。
2006年のこと、『Nature』誌にダマスカス鋼からカーボンナノチューブ(CNT)が発見されたという論文が掲載された。
現存するダマスカス剣の表層を溶かし電子顕微鏡で観察した結果、ナノチューブ鋼に特有の構造が見つかり、ダマスカス鋼やデリーの鉄柱の優れた性質がCNTによって説明できるのではないかという内容であった。
この研究が報道などの伝言ゲームを経て「デリーの鉄柱」などの「ダマスカス鋼」は「ナノチューブ鋼」であり、古代インドではナノテクノロジーが使われていたという話に発展している。
ところが「デリーの鉄柱」と「ダマスカス鋼」には、それぞれ独立した長い研究の歴史があり、両者は文化的にも物理的にも完全に別モノである。
したがって、ダマスカス鋼によってデリーの鉄柱を説明しようとする行為は、ナンセンスと言わざるを得ない。
ナノテクノロジーとする話も飛躍し過ぎである。確かにCNTがナノテクノロジーの象徴であることは間違いない。
だが、そもそもCNTとはダイヤモンドや鉛筆の芯(黒鉛)と同じで炭素の同素体である。
CNTの生成機構には未解明な要素もあるため、本当にCNTが確認できていたとしても(当然だが誤認の可能性もそれなりにある)、解かれるべき謎は、当時の原料と製鋼法によって、どのようにCNTが生成されたのかということになる。
電子顕微鏡や加工技術があってこそのナノテクノロジーなのだから当然であろう。
同じ理由で、今後、もしデリーの鉄柱からCNTが検出されたとしても(ダマスカス鋼とは根本的なレベルで違いが大きいため、その可能性は低いだろうが)ナノテクノロジーが使われたと期待する理由はない。
結論として、デリーの鉄柱とダマスカス鋼は分けて扱わねばならないし、CNTが存在するということだけでは、ナノテクロノジーを示唆することにはならないのだから、ことさら超常めいた話にするような話ではないのである。
書籍【項目32】「デリーの鉄柱」が錆びない理由:要約
デリーの鉄柱をめぐる謎については、超常論者だけでなく非合理批判の文脈からも色々と指摘されてきた。
錆びない原因も「人間の油脂による保護」、「環境のおかげ」、「高純度鉄だから」、「リン酸鉄の皮膜が保護した」、「本当は根元が錆びてボロボロ(だから錆びているのだ)」といった謎の度合いを貶める方向への「常識的な説明」が語られてきた。
だが、それらはすべて誤っているか、せいぜいのところ藁人形論法でしかない。
とりわけ、人が触ってきたことで油脂が皮膜となって鉄柱を保護したという説は、今となっては皮肉でしかない。
なにしろ人が撫でたり触ったりしてきた部分が劣化してしまい、1997年から鉄柵(もう錆びている)が設置され、現在では触ることができないのだから。
現実問題として、デリーの鉄柱の謎を解明する説は、以下の要素を満たさねばならない。
- 滑らかで黒々とした鉄肌になるような、
- 1600年も腐食性の錆から保護される強烈な原因が、
- 5世紀北インドのグプタ朝の製鉄技術で実現されており、
- それがデリーの鉄柱のみに生じた理由
これを全て満たして、やっとスタートラインに立てる。ここまで取り上げた説では、インターネット上で人気の「リン酸鉄皮膜説」のみ部分的に正しいが結論としては誤っている。その他の説はダマスカス鋼説を含め、どれもこれもお門違いである。
もっとも、デリーの鉄柱が錆びない理由が現在も未解明なのかというとそうではない。
結論からいえば「デリーの鉄柱」が大気に曝露されながら、1600年も美しい鉄肌を維持できていた理由は、鉄柱の表面が黒々とした保護性錆(かつて安定錆と呼ばれていた錆の層)によって、腐食性の錆から守られていたからである。
5世紀北インドの鍛冶職人たちは、錆びに強い鉄を得るために到達した――リン(P)が豊富な植物(カッシア・アウリキュラータ)を還元剤の一つとして使い、直接製鋼法で低温還元した塊鉄(かいてつ)を鍛造する――方法によって、潜在的に現代の耐候性鋼と同様の特徴を備えた錬鉄を産み出していたのである。
耐候性鋼とは一般にクロム等を微量添加した合金鋼であり、表面に防錆処理をせずとも大気に曝露されると緻密な保護性錆が生じるため(あたかもデリーの鉄柱のように)腐食性の錆から守られるような鋼材である。
特筆すべきは「デリーの鉄柱」の保護性錆が、意図的に増量されたリンによって成長が促進されていたことである。
つまり1600年も大気中で美しい姿を維持する黒き鉄柱は、ただの奇跡的な偶然によって生じたのではなく、相応の工夫があってこそ誕生したのである。
ただし、それでも「デリーの鉄柱」が極めて特殊な例であることも忘れてはならない。
実際に同じレシピで鍛造された他の鉄製品は、通常の錬鉄よりも大気腐食に強かったことが理論的に解明されたが、1600年も美しい鉄肌を維持する鉄は現存していない。
このことが何を意味するかというと、5世紀の北インドで生産された膨大な量の「大気腐食に強い鉄」のなかでも、組成と環境(移設による環境の変化を含む)などの諸条件が、保護性錆の成長にとって、類を見ないほど最適だった事例が「デリーの鉄柱」だったということである。
結論として「デリーの鉄柱」は、古代の技術史を大幅に修正する「真のオーパーツ」とまではいかないが、グプタ朝の鍛冶職人がいかに優秀であったのかを証明する、世にも珍しい古代の耐候性鉄だったのである。
少なくとも、漫然と奇跡的な偶然を期待するだけでは実現し得なかった現象であり、その意味で「デリーの鉄柱」は大気腐食に対する人類の初勝利と表現しても大袈裟ではないだろう。
追加【伝説と真相1】 99.72%の高純度鉄に関する謎と誤解
【伝説】
この鉄柱が科学的にも考古学的にも異常性が高い物件であることは事実である。当然、この「錆びない鉄柱」に見られる極端な耐蝕性(錆びにくさ)は、19世紀以降、多くの科学者を魅了してきたし、有名ではないが冶金学の世界では長い研究の歴史がある。
組成を分析する近代的な調査は1912年から始まるが、その結果は驚くべきもので、鉄柱そのものが99.72%の高純度鉄であることが確認されている。
これは1945年、1961年と、異なる試料の分析でも±5%程度の範囲で追認されており、紛れもない事実である。
まず、これほどの純鉄は現代でも生産が困難であるということを指摘せねばならない。
現在、世界最高の高純度鉄は2011年に日本で安彦兼次(東北大学客員教授)が80キロだけ製造に成功した99.9996%の純鉄である。
さすがに純度では21世紀の科学が勝っているが、それに迫る99.72%の純鉄を6トンも鍛造したのだから、古代インドの製鉄技術は驚嘆に値する。この事実をしてオーパーツと評価することも可能なほどであろう。
【真相】
デリーの鉄柱が純度99.72%付近の純鉄であるという話は、意外(?)にも事実である。
だが、現代の技術と比較する議論の多くは事実を誤認している。2011年に安彦兼次(東北大学客員教授)が製造した純鉄は99.9996%の超高純度鉄であり、少数点以下の微差に過ぎないと思うかもしれないが、この差は果てしなく大きい。
なぜなら安彦教授の研究によって、鉄が99.995%以上に高純度化されると、鉄の特徴が著しく変化するという新しい現象が発見されたからである。
超高純度鉄は、銀色に輝いており、塩酸に漬けても溶けなくなる。金のように柔らく加工が容易になるが、割れにくくなり切れにくい――そして錆びない。
もし、デリーの鉄柱が「超」高純度鉄であり、だからこそ錆びないというのならば、間違いなく第一級のオーパーツであろう。しかし、デリーの鉄柱は「超」がつかない高純度鉄である。
もっとも、このことでインドの鍛冶職人の評価を下げる必要はない。たとえば1960年頃の代表的な純鉄、アメリカのアームコ鉄ですら純度は99.90%である。
デリーの鉄柱を造った鍛冶職人は、99.72%の純鉄を6トンも生産し、柱頭部分には複雑な装飾を施しつつ巨大な鉄柱に仕上げたのだ。これを実現した鍛冶職人たちが超一流であったことは間違いないだろう。
追加【知識と補足1】 古代インドの製鉄と基礎知識
もしかしたら、99%以上の高純度鉄が5世紀の北インドで実現可能だったという部分に疑問を持つ人もおられるかもしれない。
だが、そもそも高炉で大量生産される現代鉄よりも、古代鉄の方が優れている場合もある。その象徴的な事例が法隆寺の釘である。
1935年のこと、法隆寺の改修工事が行われたときに、1300年前の錆びていない鉄釘(和釘)が発見されているが、この釘は純度99%を越える純鉄であった。
錆びていない理由は内部への腐蝕の進行を防ぐ緻密な黒錆(Fe3O4)によるコーティング(酸化皮膜による保護)と、木材に埋まっていたこと(環境要因)が決め手であるが、古代インドに限らず6世紀の日本でも99%を越える純度の鉄が造られている。
古代鉄の純度が高い理由は、限られた技術のなかで量よりも質を追求した場合の帰結だからである。
このことは、鉄がどのようにして造られるのかを知っておけば理解しやすいかもしれない。
そもそも自然界にある鉄鉱石や砂鉄は(サビもそうだが)「酸化鉄」である。古代には、これを炉のなかで炭素(木炭)と共に燃やし、一酸化炭素などによる還元反応で酸素を奪い取ることが鉄を得る第一歩であった。
要するに自然界にある酸化鉄から酸素を奪うわけだが、その方法には、大きく分けて「間接製鋼法」と「直接製鋼法」の二種類がある。
ひとくちに「鉄」といっても、「鉄」が硬いか軟らいか、割れるのか千切れるのかといった鋼材としての特徴は、ほぼ炭素含有量によって決まる。その炭素含有量の違いは、基本的なレベルでは製鋼方法の違いによって生じている。
まず「間接製鋼法」というのは、1200度~1500度以上の高温で鉄が液体になるまで溶融し、銑鉄(せんてつ)を得ることから始まる。
銑鉄は炭素含有量が4%以上と非常に高いため、かなり割れ易いが、成型する工程で炭素量を調整し、鋳鉄(ちゅうてつ ※1)や鋼(はがね ※2)など目的に応じた鉄鋼を得ることができる。
※1 鋳鉄(ちゅうてつ)は読んで字の如し鋳造された鉄のことだが、学術的には炭素量2.14%から6.67%で、ケイ素(Si)を含んだ鉄を指す。融点が低く、硬くて割れ易いタイプの鉄である。
※2 鋼(はがね)とは強靭さや耐熱性などを高めた鉄の総称で炭素量が0.3%から最大2%程度の鉄、あるいは、それにクロムやニッケルなどを微量添加した合金を指す。炭素が0.3%未満でもステンレス鋼などが存在するが、炭素量が適切な強い鉄という感じである。ちなみに鋼は想像を絶するほど種類が膨大である。
この方法は大量生産に向いており、現代鉄は間接製鋼法で生産されている。
ただ、それほどの高温を実現することは難しいため、間接製鋼法を発明した古代文明は、紀元前の中国と3世紀の南インドなど圧倒的に少数である。
デリーの鉄柱が造られた5世紀の北インドでは、間接製鋼法ではなく、数百度の低温で還元する「直接製鋼法」が用いられた。鉄というのは便利なもので、数百度しか出せない場合でも、還元反応を起こすことができる。
鉄鉱石を低温で還元するとスポンジ状の塊が得られるが、これを塊鉄(かいてつ)と呼ぶ。
そのままでは使えないため、飴状に熱せられた塊鉄をハンマーで叩いて成型することになるが、この作業は成型だけが目的ではない。
そうすることによって金属内部の隙間が潰れ、結晶が微細化し、不純物が排出され、鉄の品質が向上するのである。この工程を鍛造(たんぞう)という。
鍛造された鉄は錬鉄(れんてつ ※3)と呼ばれ、不純物が十分に少なければ高純度鉄とも呼ばれる。
なお、錬鉄にはスラグ(鉄滓、残存する不純物)が繊維状になって散在しているほか、溶接に適しているといった特徴があり、デリーの鉄柱の組成は典型的な錬鉄であることを示している。
※3 錬鉄(れんてつ)は炭素含有量が低い軟らかな鉄であり、融点が1500度と高い。本文では直接製鋼法で鍛造したものだけをいうように書いたが、厳密には間接製鋼法で錬鉄を得ることもできる。ただし現代では、わざわざ間接製鋼法で錬鉄を得るメリットはない。
両者を比べると間接製鋼法の方が近代的だが、だからといって得られる鉄の品質が優れているかというと、必ずしもそうではない。
直接製鋼法では低温で還元するため、間接製鋼法よりも不純物が少ないばかりか、鍛造する職人の愛と勇気が十分ならば、不純物を徹底的に排除することができる。
このように直接製鋼法で鍛造する方法には、品質(※4)の上限が高いというローテクならではのメリットがあるのだが、困ったことに木炭の確保だけで環境破壊が起きるほど生産効率が悪く、大量生産の必要性によって淘汰されてしまった。
※4 鉄は不純物が多いほど腐食しやすく品質が悪くなるため純鉄を目指すことに一定の意義はあるが、ある程度まで製鉄の知識が発達してから考える場合、炭素量を調整した鋼や合金鋼にした方が鋼材としての品質は良い。
要するにデリーの鉄柱が99%以上の高純度鉄である理由は、一流の鍛冶職人が直接製鋼法で高品質な鉄を追求した結果なのである。
これほど巨大な鉄柱を鍛造した職人の技量は称賛に値するが、少なくとも古代の技術史を覆すような種類の話ではない。
追加【伝説と真相2】 巨大な鉄柱の製造方法に関する謎と地中部分の深さ
【伝説】
高純度鉄については良いだろう。だが、そもそもデリーの鉄柱を7メートル6トンの鉄柱として鍛造する方法はどうか。これまた未解明であり、かなりのオーバーテクノロジーである。
5世紀の北インドには大型の溶鉱炉がなく、一度に精製できる鉄は20~30キロ程度に過ぎない。
そのため円盤状にした鉄を何枚も何枚も重ねて鍛接し、鉄柱に仕上げたというのが定説であった。
ところが、インド国立物理学研究所のクマール博士が、製造方法の確証を得るため、鉄柱内部を超音波が透過する速度を測定する実験によって、円盤が重なった痕跡(接合部分の実在)を確認しようとしたが、検出できなかったのである。
つまり現在の考古学の常識では、古代インドに巨大な鉄柱を造る技術など存在しないことになるのだ。
この事実は現代の古代史研究に深刻な欠陥が存在することを示唆しているのではあるまいか。
さらには鉄柱全体がより巨大な構造物の可能性もある。デリーの鉄柱は地中深くまで伸びており、大地を支配する大蛇の首を押さえつけているという伝承があるのだが、これは迷信であるにせよ、根拠がない話だとは限らない。
冶金学史の記念碑的大著でもあるベックの『鉄の歴史』(※5)には、8メートルほど掘り進んでも鉄柱が続いており、どのくらいまであるのか分からないといった記録が紹介されている。
ということは、地中部分は相当深くまで埋まっており、ことによると6トンという推定も間違えているかもしれないのだ。
※5 『鉄の歴史』ルードウィヒ・ベック著、中沢護訳。原著1888年で原題『技術的および文化史的にみた鉄の歴史』という五分冊の大著。冶金学の歴史を知るには必読とされている。ちなみに著者のベックはヒトラー暗殺未遂事件の中心人物ベックの父親である。
それに19世紀までは西欧世界の人々にとって、最大の鉄建造物としても知られていたのだから、巨大なサイズと製造方法という、この点をとってもオーパーツ性は確かであろう。
なぜならデリーの鉄柱は、近代科学が発達した西欧からは遠く離れたインドであり、しかも5世紀に造られたのだ。これほど理不尽な謎を、貴方がたはなぜ放置しているのだろう。
【真相】
まず地中部分の話だが、たしかにベックの『鉄の歴史』が記念碑的な重用文献であることは論をまたない。だが、あまり重要でない小ネタまで重視する必要はあるまい。
幸いにも1961年にASI(インド考古学会)が地中部分まで発掘調査をしており、地中は0.94メートルであることが確認されている。
だから、どこまで埋まっているかという話については、1961年より前の情報は無視すれば良い。
鉄柱の鍛造方法については、たしかにネット上で人気の円盤を何枚も重ねたという説は【伝説】の指摘が正しく、学術的にも否定されている。
だが、その後の非破壊検査で何回かに分けて接合した痕跡が確認されているため、一度の作業で造られたわけではない。
仮に一度の作業で造ったとしても「どうにかしたのだろうね。凄いね、インド人」と思うだろう。
「デリーの鉄柱」は組成の分析から典型的な錬鉄(れんてつ)であることが確認されており、腕の良い鍛冶職人がハンマー等で叩いて鍛造したことは確定事項である。
錬鉄は溶接に向いており、数ブロックずつ縦に接合すれば巨大な溶鉱炉なしでも7メートルの大鉄柱を仕上げることは可能であろう。
現代では巨大な鉄柱を直接製鋼法で鍛造するような必然性がないので、ノウハウこそないが、特別に無理な話だと考える理由もない。
たとえば高さ1メートル、直径40センチメートルの塊鉄炉で鉄柱を鍛造し、その上に2メートルの塊鉄炉をかぶせ、という手順で上に伸ばして鍛造していったという説がある。
塊鉄炉とは鉄鉱石と木炭をぶち込んで熱する炉であり、直接製鋼法で鍛造する工程のうち、鉄と不純物が混合したスポンジ状の鉄(塊鉄)を取り出す段階で壊すことになる。
そのため理に適った方法である。
筆者は製鉄の現場作業について不勉強かつ実地的な経験もないので、方法の是非を判断する能力は持ち合わせていないが、確実に指摘できることがある。
それは5世紀の鍛冶職人によって、以降1400年ほど西欧世界が追いつけないレベルの巨大な鉄柱を鍛造したという偉業は、オーパーツという文脈ではなく、当時の鍛冶職人がいかに優れていたかという観点から評価されるべきだということである。
追加【伝説と真相3】『マハーバーラタ』と「デリーの鉄柱」本当は凄いグプタ朝
【伝説】
2006年のこと、ドイツのドレスデン工科大学のペーター・パウフラー博士率いるチームが「ダマスカス鋼からカーボンナノチューブ構造が発見された」という論文を発表した。
実に驚くべき内容だが、この論文は世界で最も権威のある科学論文誌『Nature』に掲載されており、少なくともただのヨタ話ではない。
さすがに『Nature』に掲載された論文であり、古代インドにナノテクロジーが存在したとまでは主張されていないが、カーボンナノチューブが1991年にようやく発見されたナノテクノロジーの象徴であることは動かしようのない事実である。
そしてデリーの鉄柱もまたダマスカス鋼であるということは古くから指摘されてきた。つまり、この発見は「デリーの鉄柱」の耐蝕性がナノテクノロジーに起因することを示唆しているのである。
恐らくパウフラー博士はご存じなかったのだろうが、5世紀の北インドを統治したグプタ朝では、デリーの鉄柱ばかりか、全18巻20万行からなる大叙事詩『マハーバーラタ』(バラタ族の戦争を物語る大叙事詩)が編纂されている。
題材となる戦争は、編纂よりも1300年以上の昔、紀元前10世紀頃に起きたクル王朝の内紛に端を発する大戦争である。興味深いことに、この戦争そのものは史実であることが知られている。
『マハーバーラタ』(※6)というと、学術的には『イーリアス』『オデュッセイア』と並ぶ世界三大叙事詩として有名だが、本当にあった古代核戦争の記録なのではないかとも指摘されてきた。
なぜなら、古代の実際にあった戦争が題材であるにも関わらず、近代兵器がふんだんに登場するからである。
※6 『マハーバーラタ』は日本語、英語ともに核戦争にしたくて仕方がない人々による、酷過ぎる超訳もどきが出回っている。本稿では真面目な訳である『マハーバーラタ』山際素男訳2013版を想定しているが、それでも大量破壊兵器や原爆の被害を連想するような描写があるのは事実である。ただしアビドス神殿のヘリコプターが、門外漢には「本当にヘリコプターに見える」としても、「見えるだけ」だというのと同じで、底が浅くそれ以上掘り進むことができないほど陳腐な憶測でしかない。
機動性の高い航空機ヴィマーナから、核ミサイルのような超高温かつ広範囲を殲滅する大量破壊兵器アグネーヤが大量に発射され、核戦争さながらの惨状にいたる様子が克明に描写されている。
たとえば「一面の空から落下するアグネーヤに灼き焦がされた将兵は、炎に包まれた樹木さながらに燃え上がり次々に倒れていった」といった具合に…。
現代人からすれば、本当に5世紀のインド人が想像だけでこのような描写ができたのかと悩んでしまうほど、広島の惨状と酷似した描写が多いのである。
さらにはグプタ朝が栄えた北インドのすぐ西には、やはり古代核戦争の被災地ではないかと指摘されているモヘンジョダロがある。
そこから遥か西北のトルコまで目を向けると、核の冬から避難するための核シェルターである可能性が指摘されてきたカッパドキアの地下都市もある…。
北インドやパキスタンから適度に離れていることも、死の灰から逃れるためだと考えれば必然性しかない。
ともあれ、少なくとも同じ時代、同じ場所、同じ文明の下で、ナノテクノロジーの存在を示唆する鉄柱が製造され、(題材となる戦争は史実の)核戦争の正確な描写がある大叙事詩が編纂されているのだ。
こうした証拠群を前にすると、紀元前数千年の昔、北インドとパキスタンにまたがり、我々の知らない高度文明が栄えていたという仮説が必然的に生じてしまう。
この観点からすれば、古代核戦争説もまた学術的な仮説として検討する価値がありそうだ。
【真相】
項目31の本篇(書籍版)で説明したように、ダマスカス鋼は超高炭素鋼であり、デリーの鉄柱は高純度の錬鉄である。文化的にも物理的にも完全に別モノなのだから一緒に論じることに意味はない。
また、項目31の概要でも説明したように、仮にカーボンナノチューブ構造が発見されようとも、ナノテクノロジーを用いたと考える理由はない。
ただし『マハーバーラタ』という高度な文芸作品である大叙事詩と、高度な製鉄技術を必要とする「デリーの鉄柱」が、4~5世紀の北インドで誕生したことは、【伝説】が指摘するように偶然ではないだろう。
当時は北インドを統一したグプタ朝の最盛期にあたり、知的営為の多くが高度に発展した黄金時代だったことが知られている。
その発展ぶりは驚くほどで、たとえば傷痍軍人などの顔面再建手術が造鼻術として行われていたが、これは現代の頭頸部外科で行われる整形外科術の元祖のような技術であり、西欧世界のそれよりも1000年以上も先んじているほどである。
グプタ朝の製鉄も、歴史的に南インドのダマスカス鋼(シリアのダマスカス剣の鋼材)ほどには注目されず、近代科学に対する直接的な影響(※7)を与えていないため、研究がやや薄いが、だからといって劣るわけではない。
※7 ダマスカス鋼は近代冶金学に大きな影響を与えている。この伝説的な鋼が「UFOの素材だったのではないか」とするデニケン説は空想に過ぎないが、実在していたことは事実である。惜しむらくは製造方法が失われてしまったことであるが、19世紀初頭に、かの有名なマイケル・ファラデーが「ダマスカス鋼」の謎に挑戦し、これが科学的な合金研究の萌芽となった。ファラデー個人の研究は失敗したが、およそ100年後に予期せぬかたちで実を結ぶことになる。それが20世紀初頭に発明された現代の錆びない鉄「ステレンス鋼」である。「ダマスカス鋼」は本当に人気があり、現代でも大量の研究が存在するため、興味がある人は調べると良い。
そもそも古代インドの製鉄は、アレキサンダー大王の時代から優秀さが知れ渡っており、インドのお家芸でもある。
「デリーの鉄柱」ひとつとっても、近代科学の発展期にいたってもなお西欧世界が同じ規模の鉄製品を生み出すことができず、20世紀初頭にステレンス鋼を発明しようとも「デリーの鉄柱」に匹敵する耐候性鋼を造り出すことはできていなかった。
だからこそ、グプタ朝の素晴らしさを称賛すれば済む話なのだが、困ったことに、古代の宇宙飛行士説や古代核戦争説の提唱者や信奉者、さらには懐疑主義側(の一部の人々)にしても、恐らくは自覚していない偏見によって、しばしば議論の質を低下させがちである。
その原因は、黎明期から20世紀中頃までの考古学(という学問を成立させ古代史の基本的枠組を確立した功績からすれば些細な問題に過ぎないが)の暗黙の前提に、西欧から離れて古くなるほど文明の水準を低く見る傾向があったからであろう。
それも無理からぬことで、産業革命を実現し近代科学を成立させた欧米の列強が、人類史上でも極端に突出した文明であったこと、良くも悪くもキリスト教的世界観の影響が強い社会から産まれたことから、ある程度は必然的に生じた問題である。
結果、そうした偏見の影響によって、ビリーバーは古代インドが実現可能だった水準の技術を不当に低く設定し、エイリアン等の助力が必要だったとほのめかしてきた。
同じく非合理批判に情熱を燃やす人々の一部も、ヨタ話を棄却するところまでは妥当な議論を展開していても、しばしば勢い余って、非合理な「常識的説明」や、「やりすぎた過小評価」をしてしまうこともあったのである。
振り返って欲しい。古代ギリシア・ローマは、あまたの古代文明のなかで、もっとも高度な文明として認識されてきた。
ところが、その古代ギリシアに対しても、キケロの著作など遥か昔から記録があったにも関わらず、「知的で優れてはいたが哲学など観念論の世界に夢中で、工学などには無頓着だった」という先入観が支配的であった。
この認識が覆ったのは1970年代以降の研究が成果を上げてから(※8)である。
それでも1900年に発見された「アンティキテラの機械」がギリシア工学再評価後の認識よりも、さらに高度で精密な機械(※9)であることが認められたのは21世紀になってからであった。(※10)
※8 古代ギリシアの機械工学は、ヘロン関係の文献やキケロの著作などに詳しく記されていたし、ルネサンスにはダヴィンチが記録を元に再現などを試みていたが、長らく実在ではないとして軽視されていた。これが1970年代に、ようやく古代のテクノロジーを再評価する動きが始まり、新しい発見や研究が進むことで、神殿の自動ドアや聖水のコイン式自動販売機やヘロンの蒸気機関などの実在性が認められることになったという歴史がある。
※9 1970年代には高精度の天文計算機であることが判明していたが、デニケン等が古代宇宙飛行士説と絡めたせいでキワモノ扱いされてしまう。これが18世紀から現代でも最高の時計職人の仕事に匹敵する精密な歯車機構であるという、より高い評価が確立したのは2005年に発足した大規模プロジェクトの成果が出てからのことである。
※10 「アンティキテラの機械」は、古代ギリシアの技術史を根底から覆す(極端な過小評価をしていたことを現物によって実証した)今のところ唯一の「真オーパーツ」である。1970年代にはかつてない高度な天文計算機であることが判明していたが、2005年に発足した大規模プロジェクトによって内部構造の解明が大幅に進んだ結果、さらに評価を高めることになった。近現代の最高の時計職人の仕事に匹敵する極めて複雑かつ合理的な歯車機構であるばかりか、携帯可能なサイズにするための小型化の工夫が洗練されており(ミリ単位の部品もある)、親切な取り扱い説明書が掘り込まれているなど、その完成度が明らかに「高度な完成品」だったからである。一発でゴールできる製品ではなく、試行錯誤やそこにいたるために発展した技術が多数存在していることが確実であることが、特に重要であった。『アンティキテラの機械』ジョン・マーチャント著に詳しい。
1865年にフランス南部で、紀元前2000年頃の墓から出土した穴あき頭蓋骨群も然りである。
当時は当たり前のように「食器にしたか拷問したか脳みそをチューチュー吸った痕跡」だと決めつけられてしまったという。
発掘から数年後にポール・ブロカ(脳科学の父の一人)が個人的な調査の結果、脳内出血の治療痕、つまり外科術の痕跡としか考えられないという説を立てたが、本人含め誰も重要視せずに忘れられてしまった。
なにしろ人類史上もっとも栄えたと自負していた19世紀の西欧世界では、開頭術の成功率がすこぶる低かったのである。
現存する記録の一つでは、ロンドンで7年間に32例の開頭手術が行われた結果、生存は8名という有様で、「古代の野蛮人」がこれほど難易度の高い外科手術が出来たなどとは信じられなかったのである。
この認識が変化したのもまた20世紀中後半になってからのことである。
現在では紀元前150年の中国、2世紀のドイツ、ルーマニア、古代ヨーロッパのケルト人、紀元前2000年のフランス南部、イングランドのドーセッド、20世紀のアフリカ一部地域(80年代にも技術が現存しており、治療によって頭蓋骨が半分無くなったまま生きている人物が見つかり調査されている)など、打撲などの脳出血に対する確立された外科術だったことがわかっている。(※11)
※11 『古代の発明』 ピーター・ジェームス、ニック・ソープ
有名なインカでは214例のうち72%が術後も年単位で生存していた(※12)ほどである。
他にも古代インドの医学といえばアーユル・ヴェーダばかりが有名だが、精巧な手術道具が多数記録に(※13)残っており、現実的な医療技術の高さを伺い知ることができる。ふた昔前なら拷問道具とされたことだろう。
※12 古代で開頭術がやたらと発達していた理由として、武器による頭部への打撲ばかりか、イヌサダムナシなどの脳に寄生する寄生虫が一時期人類を宿主にしていた可能性も指摘されている。中国や現在のルーマニア付近には頭痛で目が見えなくなった患者の頭から「ムカデ」を摘出し治療したという逸話が残っているという。もっともこの説がどれほど妥当なのかは不明だが。
※13 『闇の世界の招待状』 リチャード・ザックス
ここで目を閉じて想い描いて欲しい。
当時最盛期を極めた4~5世紀の北インドには、グプタ様式を産み出した才能豊かな芸術家がいた。デフォルメによって美が強調された彫刻が産まれた。鼻がもげた軍人のために自家移植を発明した天才外科医もいた。
芸術性の高い通貨を鋳造し、貨幣経済を発展させた優れた官僚がいた。仏教の学問的研究を成熟させた哲学者がいた。土着の信仰を洗練させた宗教家もいた。
1000年以上も前に起きた戦争なのに「火矢の雨」を原爆レベルの破壊力で描写し、見てきたように吟ずる詩人もいた。6トンに及ぶ技巧を凝らした大鉄柱を99.72%の高純度鉄で造り上げた屈強かつ腕の良い鍛冶職人たちもいた。
そう、西欧がルネサンス期に入る1000年の昔にありながら、北インドにはこれほど優れた文明があり、才能豊な人々が躍動する活気に満ちた世界があったのだ。
なればこそ、その芳醇な文化を生み出した先人もまた、私たちと同じく温かい血のかよった普通の人間であり、性格が良い奴も悪い奴も共存していたような、実在の人間社会であったことを想い描けたならば、親しみを感じるではないか。
少なくとも異世界への好奇心を抱くことはあっても、核兵器だのナノテクノロジーなど無理矢理な話を持ち出して、リアルで活力ある古代インドの姿を台無しにする必要などないし、意義もないのである。
どうか間抜けな話で偉大な先人を貶めるような真似はしないでいただきたい。